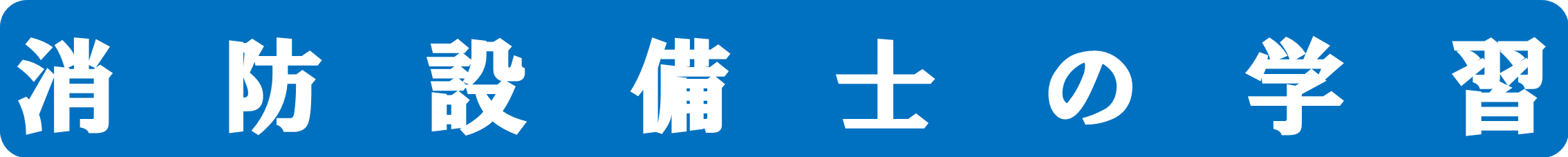消防設備士とは?業務、種別、難易度、何に役立つ?
消防設備士とは、火災の際に使用・作動する消防用設備等について専門的な知識もつ人です。また消防設備士の資格は国家資格であり、様々な消防用設備等に種別が分けられており、その工事や点検については消防設備士の独占業務になります。
手に職を持つという意味でも、消防設備士はお勧めです。
業務について
基本的に消防設備士の業務は、工事と点検になります。
先に述べた通り、消防用設備等は様々種類があり、その種類に応じた資格を持つ人だけが、工事や点検等を行う事が出来ます。(一定規模以下であれば、資格無しでも点検出来る場合もありますが。)また消防設備士さんは、自分で工事もやる方が多いので、職人と消防設備士を兼ねている方が多いと感じます。ただ資格の種別によっては工事が出来ない人もおり、点検業務だけを行う会社等もあるので、働き方は人それぞれです。
種別・試験について
種別は特類、第1類から第7類まであり、特類は甲種、第1類から第5類は甲種又は乙種、第6、7類は乙種と全13種類の試験があります。
種類が多いので、全部取るのにどれだけ時間がかかるのかと心配される方もいるかも知れませんが、本気で最短で目指せば約1年ぐらいで取得することも可能です。
ここでは詳しくは述べませんが、同日に2つ試験を受けたり、第1~5類は甲種を取れば乙種は含まれているので実質年に5回ぐらい受験することで全制覇することも可能です。
試験の手数料は、甲種が5,700円、乙種が3,800円となっており、また免状については1種類について2,900円の手数料がかかります。
なので、全部1発で取得すれば5,700×6+3,800×2+2,900×8=63,200円という計算になります。
特類
特殊消防用設備等(従来の消防用設備等に代わり、総務大臣が当該消防用設備等と同等以上の性能があると認定した設備等)
第1類
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備
第2類
泡消火設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備
第3類
不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備
第4類
自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、複合型居住施設用自動火災報知設備
第5類
金属製避難はしご、救助袋、緩降機
第6類
消火器
第7類
漏電火災警報器
資格取得の難易度とお勧め順について
消防設備士の資格は全般的に、国家資格とされる他の試験に比べると比較的簡単です。
その中でも、取りやすさ等を考慮したランキングを以下に並べてみました。(個人的主観で、専門的知識は無いと考えています。)
第1位 第6類 消火器 難易度★ 活用★★★★★
難易度及び活用の頻度を考えると圧倒的に第6類をお勧めします。難易度はおそらく消防設備士の試験の中で一番簡単です。また、消火器は基本的に1番最初に必要となる消防設備であり、多くの人にとって一番身近な消防用設備等であるからです。
第2位 第5類 避難はしご等 難易度★★ 活用★★★★
難易度もそこそこで、比較的身近にある消防用設備等です。共同住宅やビルにはほぼ設置されているので、比較的イメージがつきやすいのも資格取得には良いと思いますし、乙種だとより資格の取得はしやすいですし、身近にある設備を適切に点検することも出来ます。
第3位 第4類 自動火災報知設備等 難易度★★ 活用★★★
>これも難易度もそこそこで、比較的身近にある消防用設備等です。天井についている火災を知らせる設備はみなさん分かると思います。これも比較的イメージがつきやすいのも資格取得には良いと思いますし、乙種だとより資格の取得はしやすいですし、身近にある設備(感知器等)が適切に設置されているかなどもわかるようになります。
第4位 第7類 漏電火災警報器 難易度★★★ 活用★★
ここからは、試験の難易度が少し難しいです。専門的な知識等がありアドバンテージがある方は取得もしやすいと思いますが、一般の方が取るのは少し大変です。また、そこから活用方法を考えると、やはり仕事としてやっていく為には必要ですが、あまり他のことに役立つとは考えられないため、4位としています。
第5位 第1類 消火設備等 難易度★★★ 活用★
これ以下は正直、一般の人が取る資格としては難易度や活用方法等を考慮するとあまりお勧め出来ません。一応ランキングにはしていますが。
基本的に大きなビル等に設置されている消防用設備等になるため、そもそもどんな物かもイメージしづらいと思いますし、活用方法もあまり思い浮かびません。屋内消火栓はギリギリ扱う人もいるかなと思ったので4位にしました。
第6位 第2類 泡消火設備等 難易度★★★ 活用★
基本的に大きなビル等に設置されている消防用設備等になるため、そもそもどんな物かもイメージしづらいと思いますし、活用方法もあまり思い浮かびません。泡消火設備は地下駐車場等で使用されているため、まだ関わる人がいるかもしれないとして5位にしました。
第7位 第3類 不活性ガス消火設備等 難易度★★★ 活用★
基本的に大きなビル等に設置されている消防用設備等になるため、そもそもどんな物かもイメージしづらいと思いますし、活用方法もあまり思い浮かびません。
第8位 特類 特殊消防用設備等 難易度★★★★ 活用★
普通の消防用設備等ではない、何かしらの特許をとっているものや、大臣認定等を貰っているような設備など特殊なものについて必要になる資格であり、そもそも案件自体少ないです。また専門的過ぎるので、本職の人しかお勧めはしません。
まとめ
今回は消防設備士について説明しました。資格の取得自体はしやすいので、スキルアップの為にはかなりお勧めの資格になります。しかし、一部は専門的なため本職でないと役に立たない資格でもあります。自分に必要だなと感じた人はぜひ取得を目指してみてください。
よく読まれている記事一覧
» 防火管理者ってなに?1分でわかるシリーズ、防火管理講習、防災管理者との違い、根拠法令
» 収容人員ってなに?1分でわかるシリーズ、なぜ必要なのか、把握しておかないとヤバイ?、計算方法、根拠法令
» 特別高度救助隊ってなに?1分でわかるシリーズ、救助隊より凄い?、自治体ごとの違い、どうやったらなれるの?
» 救助隊ってなに?1分でわかるシリーズ、正式名称、様々な消防の特殊部隊、消防隊との違い、どうやってなるのか、法令根拠について
カテゴリー一覧
» 消防法の解説
» 消防用語集
» 消防設備士の学習
» 全国の消防組織
» 消防の予防を学ぶ
» 防災を学ぶ
» 建築と消防